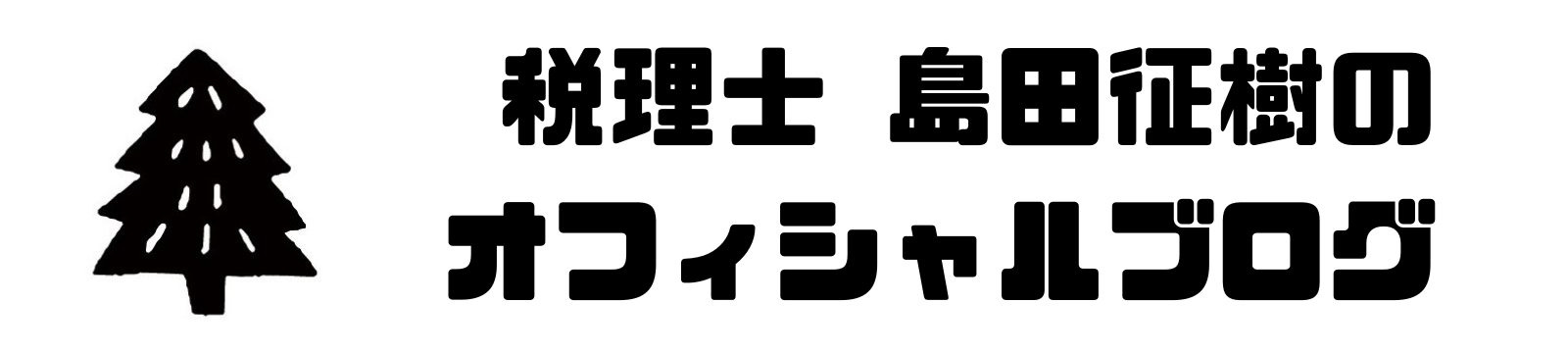経営者なら一度は聞いたことがある自己資本比率。
一般的に、高い方が財務が安定していると評価されますが、今回は評価にあたってのポイントをお話ししていきます。
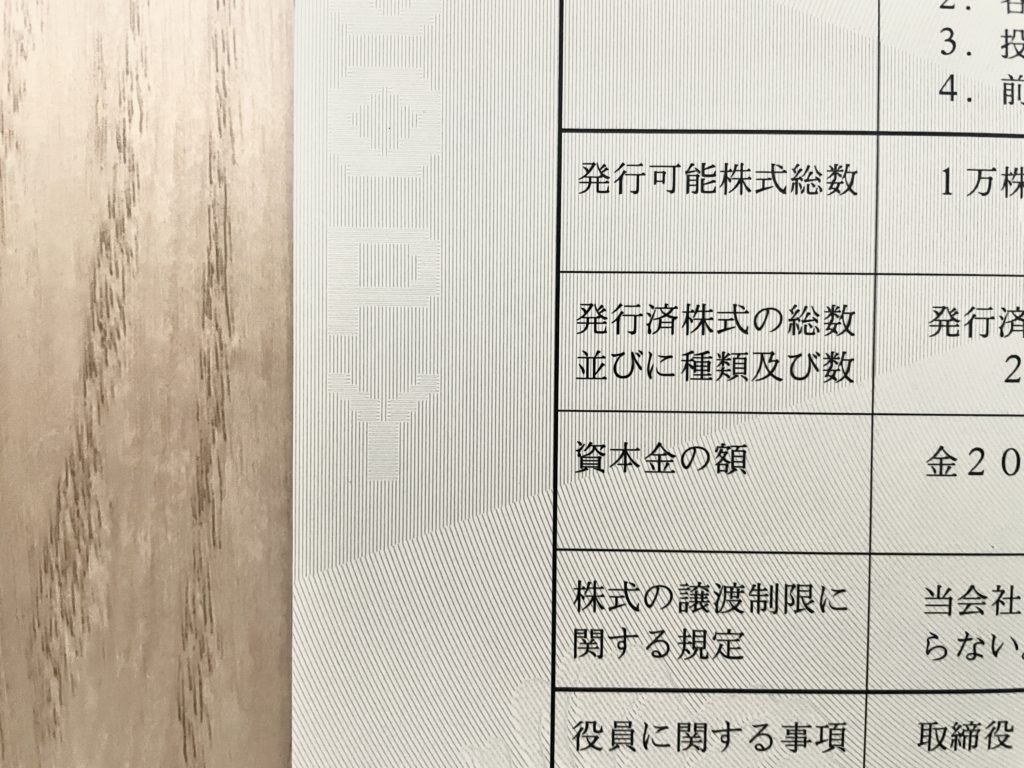
自己資本比率の意味をおさらい
自己資本とは、その名の通り、自分の懐から出したお金です。多くの中小企業の場合は、経営者やその親族、または共同創業者から調達したお金が自己資本(=出資)となっています。
自己資本に相対するのが他人資本です。その大部分を占めるのが金融機関からの借入金であり、中小企業の場合は、地元の地銀や信用金庫、日本政策金融公庫から調達しています。
そして、自己資本と他人資本の合計を総資本といいます。したがって、自己資本が総資本に占める割合は、「事業に必要なお金をどのくらい自分の財布でまかなえているか」を意味します。これが自己資本比率です。
自己資本比率=自己資本/総資本×100(%)
一般的に、この割合が高ければ高いほど、「返済の必要がない自己資本で経営できている」ということになり、経営は安定していると評価されます。これはこれでその通りではあります。ただ、逆に低いからといって即刻焦る必要もありません。
ポイントは調達した資金を使ったとき
結論から言うと、自己資本比率が高い低いということよりも、調達した資金がどのように使われているかが重要になってきます。
ということで、自己資本比率が極端に低い状態のときに、そこから考えるべき着眼点をお伝えします。
一般的に自己資本率が30%以上だと優良企業と評価されているのですが、今回は自己資本比率が10%の企業を例にお話ししていきます。
たとえば、経営者が100万円を出資して会社を設立した場合、自己資本は100万円で現金も同額の100万円があることになります。貸借対照表でいうと、資産の部(左側)に現金100万円、資本の部(右側)に資本金100万円が記載されているということです。
次に、この経営者が銀行から900万円の資金調達をすることができたとします。この時点で、現金は1,000万円、自己資本は100万円、借入金は900万円あり、自己資本と借入金を合計した総資本は1,000万円になります。
このときの自己資本比率は、「100万円(自己資本)/1,000万円(総資本)」で10%です。
ただ、900万円の借入をしたと同時に、900万円の現預金が増えるので借入金は返そうと思えばいつでも返せます。ですので、自己資本比率が10%であってもその時点では財務が危険というわけではないのです。当たり前といえば当たり前の話です。
では、どういう状態になったら財務が危険になってくるのでしょうか。それは調達した資金を使ったときです。
先ほどの例で、銀行から調達した900万円の全額を機械の購入に充てたとします。そうすると、資産の総額は1,000万円のまま変わらないのですが、その内訳が、現預金100万円、機械900万円に変わります。
ここで注意すべきなのは、機械といった設備投資は、一般的に利益の獲得までに時間がかかるということです。
何が言いたいのかというと、その利益の獲得が遅れて、仮にその獲得が1年後になると、手元にある資金100万円で事業を続けていかなければいけない状態になる、ということです。
一方で、借りたお金をいわゆる運転資金のような使い方をした場合は、売掛金や在庫が予定通り回収できれば、資金繰りに困ることはありません。
要するに、自己資本比率が多少低くてもその状態で資金繰りが上手く回っていれば、そこまで囚われ過ぎる必要はないということです。
自己資本比率が実態と乖離していないか
最初に紹介した算式のとおり、自己資本比率は貸借対照表の数字を使います。
この点において、その貸借対照表上の自己資本と他人資本の区分が、実態と違う可能性があることに注意しなければいけません。
たとえば、経営者やその親族から、出資ではなく、借入金という形式で資金を調達している場合は注意が必要です。
というのも、貸借対照表ではこのような、いわゆる役員借入金が他人資本の区分で表示されているからです。
役員借入金は、借入金とはいえ、返済の予定がなければ自己資本(=出資)と性質は同じです。したがって、その実態に沿った自己資本比率を求めるのであれば、役員借入金も自己資本に入れて計算することになります。
ちなみに、実際に金融機関が自己資本比率を計算する際はこの点を考慮してくれます。ですが、会社側からこの点を説明できればより望ましいでしょう。
まとめ
自己資本比率に限らず財務指標をみるときには、数字の高い、低いに一喜一憂するのではなく、中身(実態)や他の財務指標との関係性を注視することが大切です。
◆編集後記
もう3月も最終週ですね。
全く春を感じていませんので、桜が散る前に花見でも行こうかと。
◆家トレ日記
逆立ち腕立て10回×3セット
1分間HIIT
◆ 1day1new
近所のダックワーズ
メディア情報
セミナー情報
プロフィール
メニュー
お問い合わせ