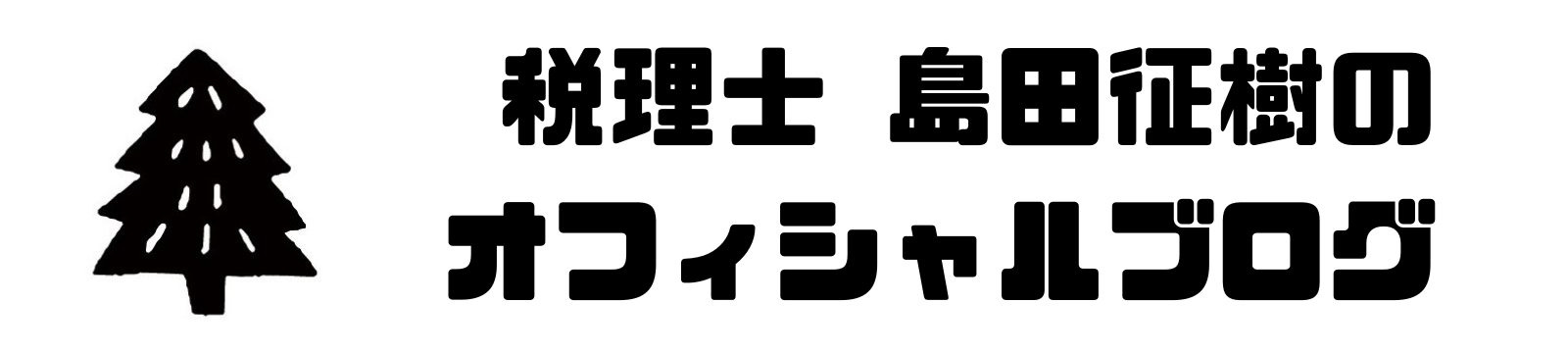こんにちは、島田(@mshimada_tax)です。
経常運転資金は会社を継続させるために、最低限手元に残しておくべきお金です。
これを自己資金でまかなえない場合は、金融機関から借りることになります。
そして、経常運転資金は、一度金融機関から借り入れることができたら、その分は返済しなくていい、と言われています。
本記事ではそれは本当なのかということ深掘りしていきます。

債務償還年数の算式から読み解く
経常運転資金が本当に返済不要な資金だといえるのか、債務償還年数の算式から紐解いてみたいと思います。
債務償還年数とは、いまの業績だと借りたお金をどれくらいの期間で返せるのか、という指標です。
一般的に、10年以内だと銀行から借り入れしやすいと言われてます。
算式は以下のとおり。
債務償還年数=(借入金残高 − 経常運転資金)÷(税引後利益 + 減価償却費)
この算式でみてわかるとおり、借入金残高から経常運転資金を差し引いて計算します。
いまいちど、経常運転資金の意味をおさらいしておきましょう。
経常運転資金は「入金を待っているお金」から「支払を待ってもらっているお金」を差し引いたもの、です。
たとえば、80円で商品を仕入れて、100円で売ったときに、代金の支払いと受け取りが1か月後だったとしましょう。
このときにその1か月間、本来手元にあるはずの100円(「入金を待っているお金」)は資金不足になりますが、逆に本来支払っているはずの80円(「支払を待ってもらっているお金」)は資金に余裕ができることになります。
言い換えれば、仕入れて売るという商売をするサイクルのなかで、両者の差額である20円は最低限手元に残しておかなければいけない資金、ということになります。
正式な算式で表すと次のとおりです。
経常運転資金=売上債権(受取手形や売掛金)+ 棚卸資産(在庫)ー 仕入債務(支払手形や買掛金)
前段の売掛債権や棚卸資産は、現金化されるまで入金を待っているものです。
後段の仕入債務はその逆で、支払いを待ってもらっているものです。
ここでもう一度債務償還年数の算式に戻りましょう。
この算式の前半である、「借入金残高 − 経常運転資金」が意味するところは、会社の返済能力を判断をするときに、手元に残しておかなければいけいない部分(=経常運転資金)はそもそも借入金残高に加えずに考えてくれる、ということです。
ですので、経常運転資金は返済不要なものだと考えられている、といえます。
経常運転資金の返済原資から考える
普通に考えると、借入金の返済原資は将来獲得する予定の利益です。
金融機関も、これをあてにお金を貸してくれます。
一方で、上記の算式のとおり、経常運転資金を構成する(算式上プラスになる)のは、受取手形や売掛金といった売上債権です。
この点で、受取手形や売掛金は一時的に入金を待っているもので、時間が経てば現金化されるものです。
したがって、経常運転資金分の融資は、将来利益がなくても返済できるものです。
掛け取引の商慣習上、売上債権の回収が次の投資までに間に合わないために、経常運転資金を手元に残しておく必要があり、それを金融機関からの借入で賄っているのです。
極論をいえば、ないお金を借りているわけではなく、一時的に手元にないお金を金融機関から自社の口座に移動させているだけであり、その移動料として支払利息を払っている、というのが経常運転資金を借り入れているときの状態といえます。
したがって、経常運転資金は究極的には返す必要のない資金なのです。
とは言いつつ返さないといけない
ところが、実際は経常運転資金分の借入金を毎月返済している会社がほとんどです。
借入金であれば、本当は金融機関のお金なので、返さなくてもおとがめなし、というわけにはいきません。
それなら、債務償還年数の算式上、借入金残高から経常運転資金を差し引いているのはやっぱりおかしい、と思われてる方もいるかと思います。
ですが、そもそも前提が違います。
経常運転資金を毎月返済していること自体が、本来の経常運転資金の性質と合っていないのです。
毎月返済していると、当初借りた経常運転資金分の現預金が手元から減っていってしまうことになります。
ですが、経常運転資金は常時手元になければいけない最低限の資金です。
何が言いたいのかというと、経常運転資金を借りるなら、「借りっぱなし」の状態を作ることが理にかなっているということです。
「借りっぱなし」とは、期限が来たら返済し、それと同時に必要な経常運転資金を借りる、を繰り返していくことをいいます。
これが理想ですが、それができない場合は、毎月返済でも減った分の借り直しを繰り返せないかを、金融機関と協議することをおススメします。
まとめ
とにかく、経常運転資金は経営の生命線です。
途切れることがないように資金繰りの管理をし、必要であれば資金を保てるように金融機関と交渉しましょう。