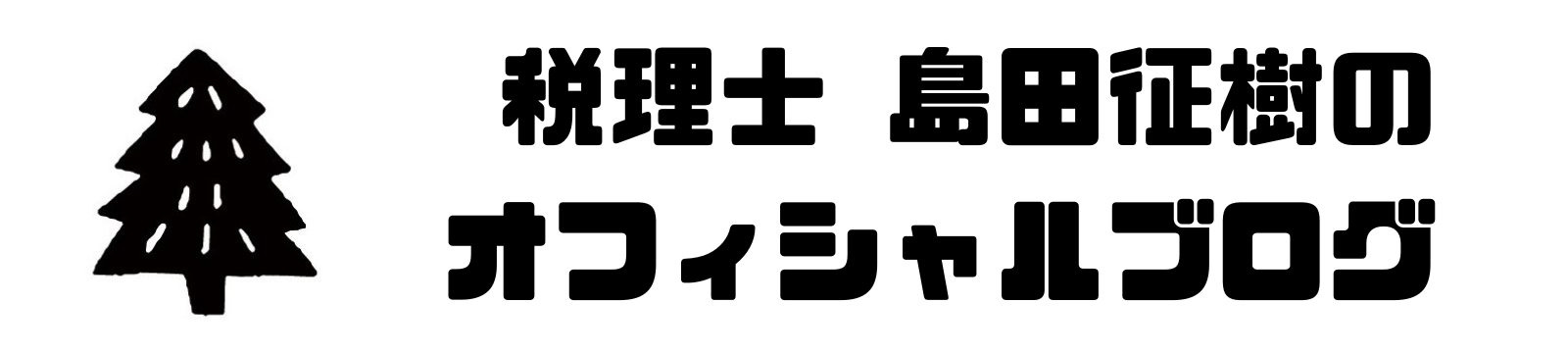4月になり新年度を迎えたタイミングで、最新の業績予測を立てている会社さんも多いのではないかと思います。
今回は、業績予測を立てる際のちょっとしたポイントをお伝えしていきます。
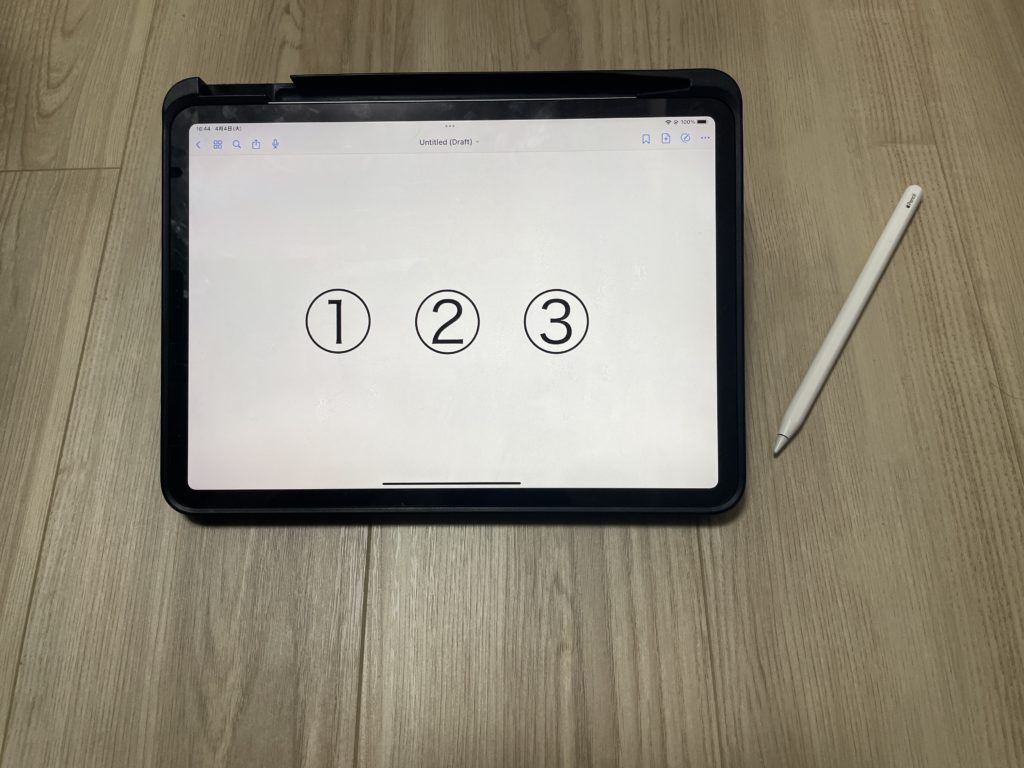
予測を立てる目的
この話をするにあたっては、そもそも、なぜ架空の予測を立てる必要があるのか、という理由を明確にしておかなければいけません。
さっそく結論からいうと、実績と対比してギャップを把握するため、という大きな理由があります。
というのも、実績という結果の数字だけをみても、それを次の年度の経営に活かすことは難しい、ということがあります。より具体的にいうと、顧問税理士さんからもらう決算書だけをみて、そこから今後の対策を練ることは難しいですよね。
それもそのはずで、数字は何かと何かを比較することで活きます。
予測があることで、実績の数字に関して、なにが、どれだけ、いつから、なぜそうなっているのか、を探ることができるということです。
つまり、予測と実績のギャップを把握することで、対策を立てることができる、ということになります。
業績予測の立て方
業績予測とは、将来ある時点で会社がどのような状態になっているかを予測することです。実績を分析するのは得意だけれども、予測は苦手という方もいらっしゃるので、予測のちょっとしたポイントをお伝えしていきます。
最低3つのシナリオを考える
業績予測を立てるときには、最低3つのシナリオを考えることをおススメします。この3つとは、「メインシナリオ」、「グッドシナリオ」、「バッドシナリオ」です。
「メインシナリオ」は、現状でもっともそうなる可能性が高いと見込まれるシナリオです。言い換えれば、アンラッキーもラッキーも起こらないと仮定した場合の、いま考え得る最も精度の高い予測ということになります。
「グッドシナリオ」は、現状は確定していないラッキーな物事が起こった時のシナリオです。たとえば、自社のビジネスにとって非常に有利に働く法改正が国会で審議されている場合に、それが可決される、というようなことです。
「バッドシナリオ」は、「グッドシナリオ」の反対です。つまり、現状は確定していないアンラッキーな物事が起こった時のシナリオということになります。
たとえば、先ほどの法改正であれば自社にとって不利な法改正であったり、いま倒産しそうな得意先があればその倒産が現実になったり、というようなことです。
3つのシナリオが必要な理由
なぜ3つも必要なのかというと、自社の経営環境に関わる良い面、悪い面の両方を俯瞰的に考えることができるからです。
というのも、楽観的な経営者、悲観的な経営者、どちらもいらっしゃると思いますが、どちらであっても両面から経営を考えることが大切です。
片方を考えて片方は見落としている、ということがないように、「メインシナリオ」に加えて「グッドシナリオ」と「バッドシナリオ」を考えるということをおススメしています。
なお、ここでいう良い面と悪い面は、それぞれ、外的な側面と内的な側面から検討するとより正確なシナリオを立てやすくなります。
外的な側面とは、いわゆる自社の外で起こる物事であり、外部環境ともいえます。先ほどの例で言うと法改正の影響が当てはまるでしょう。
ちなみに、詳細な説明は割愛しますが、この外的な側面を検討するときに役立つフレームワーク(枠組み)としては、PEST分析というものがあります。
反対に、内的な側面とは、自社の中で起こる物事であり、内部環境ともいえます。たとえば、新製品の開発や主力社員の離職といったことです。
まとめると、自社のビジネスの行く末を良い面と悪い面の両方からみるために3つのシナリオが必要であり、良い面と悪い面を検討する際のテクニックとして外的・内的な側面からのアプローチが有効、ということになります。
予測したら必ず検証をする
最後に、最も大切なことではありますが、業績予測をしたら必ず実績と比較することを忘れてはいけません。
というのも、せっかく3つのシナリオを予測できたとしても、それを踏まえて検証しなければ予測の意味がないからです。
ここで念頭に置いておきたいのが、結果的にシナリオが外れても全く問題ないということです。
なぜなら、外れたとしても「予測の段階でこう予想していたけれどもそうはならなかった。だからこういう結果になった。」という分析ができるからです。もし、業績予測を考えていなければこの分析もできません。
つまり何が言いたいのかというと、冒頭にお伝えしたとおりで、業績予測の数字と実績の数字を比較してはじめて数字が活きる、ということです。
まとめ
業績予測は、実績と違い、作ろうという意思がなければできないものです。今回の記事がその意思が起こるきっかけになれば幸いです。
◆編集後記
昨日は先日登壇したセミナーの録画をみていました。
やはり喋り方のくせってあります。
直すべきところは直していきます。
◆家トレ日記
BOOST ATHLETES
家でここまで鍛えられる3分間の最強大胸筋トレーニングを公開!!【胸の4箇所,下,上,内,外側】
https://www.youtube.com/watch?v=NxJTtwZco_0&t=291s
◆ 1day1new
ある食材探し
メディア情報
セミナー情報
プロフィール
メニュー
お問い合わせ